🟦 なぜ「助けすぎ」てしまうのか?〜教育とトラウマの影響から境界線を取り戻す方法〜
「困っている人を助けろ」「優しい人間でいろ」という教育や家庭での刷り込みは、多くの場合、善意や道徳心を育てる意図があります。
しかし機能不全家庭やトラウマを抱えた人にとって、この言葉は少し違う意味を帯びやすいのです。
✅ 子どもの頃、親の機嫌をとるために「助ける役割」を担った
✅ 家族の不安や怒りを和らげるために、自分の気持ちを後回しにした
✅ 「いい子」でいないと愛されないと思い込んでしまった
こうした経験が積み重なると、「助ける=存在価値」「優しくする=見捨てられないための条件」という無意識の信念が心に根づきます。
その結果、本当は「この人、やばいかも」と感じても、怖くて冷たくできず、むしろ優しくしてしまう。結果的に相手から好かれてしまい、抜け出せない関係を作ってしまうのです。
🟦 怖い人にほど優しくしてしまう心理
✅ なぜ「怖い相手」に優しくしてしまうのか?
これは 「トラウマ・ボンド(Trauma Bond)」 と呼ばれる現象に近いです。
トラウマ環境で育った人は、「怖い人に優しくすることで身を守る」という戦略を身につけます。幼少期に:
• 怒りやすい親に対して、ご機嫌をとることで暴力や暴言を避ける
• 支配的な大人に対して、従順でいることで安心を得る
こうした「生き延びるための戦略」が心に深く刻まれているのです。
大人になってからもその戦略が無意識に作動し、怖い人や攻撃的な人ほど「優しくしなきゃ」「嫌われないようにしなきゃ」と感じ、結果的に相手から好意を持たれてしまう。
しかしそれは本当の好意ではなく、相手にとって都合のいい存在として扱われるリスクを含んでいます。
🟦 自己犠牲の背後にある「自動思考」
認知行動療法では、行動の背後には「自動思考(瞬間的に浮かぶ信念や思い込み)」があると考えます。
例えば:
• 「助けないと私は冷たい人間だ」
• 「優しくしないと嫌われる」
• 「断ったら攻撃される」
• 「人に役立たない私は存在する価値がない」
これらは現実ではなく「心が作ったストーリー」です。しかし長年刷り込まれているため、事実のように感じられてしまうのです。
🟦 優しさと境界線は別もの
「優しい人」と「境界線を守れる人」は同じではありません。
むしろ、境界線を引ける人ほど、長期的に見て本当の意味で優しい存在になれます。
✅ 境界線がない優しさ
• 相手のために身を削る
• 嫌でも「NO」が言えない
• 逆に相手を依存させてしまう
✅ 境界線のある優しさ
• 自分の体力や心の余裕を守りながら助ける
• 危険な相手からは距離を取る
• 相手が自立する余地を残す
📌 ポイントは、「優しさ=なんでも差し出すこと」ではなく、「優しさ=自分と相手を両方守ること」という価値観の切り替えです。
🟦 「助けたい衝動」を整理するワーク(認知行動療法)
認知行動療法(CBT)では、自分の自動思考と行動パターンを見える化することで、変化のきっかけを作ります。
以下は「助けすぎループ」を断ち切るためのワークです。
✅ ステップ1:状況を記録する
• 例:「友達から『お金がなくて困ってる』と言われた」
✅ ステップ2:その時の自動思考を書く
• 「助けなきゃ嫌われる」
• 「助けないと見捨てられる」
✅ ステップ3:感情をスコア化する
• 不安80%、罪悪感70%、怒り20%
✅ ステップ4:別の考え方を探す
• 「断っても本当に大事なら離れていかない」
• 「自分の心を守るのも助けることの一部」
✅ ステップ5:実際の行動を変える
• 「今日は難しいけど、◯◯を提案する」
• 「お金は出せないけど気持ちは応援する」
こうして「助けたい衝動」にブレーキをかける練習を積み重ねると、心が次第に楽になっていきます。
🟦 「やばい人」に優しくしてしまう心理
不思議なことに、危険な匂いがする人ほど惹かれたり、怖くて優しくしてしまうケースがあります。
心理学的にいくつかの背景があります。
✅ 恐怖に基づく服従
子どもの頃に暴力やモラハラを経験すると、「怒らせないようにする」反応が染みついてしまう。
✅ 承認欲求の逆転
「やばい人にすら必要とされれば、私は価値がある」と無意識に感じてしまう。
✅ トラウマの再演(trauma reenactment)
過去に馴染んだパターン(支配・服従)を無意識に繰り返してしまう。
📌 これは「あなたが弱いから」ではなく、心の深層に刷り込まれた自動反応です。
だからこそ「気づくこと」「パターンを変える練習をすること」が回復の第一歩になります。
🟦 境界線を取り戻すステップ
✅ 1. 身体感覚に注目する
「嫌だな」「怖いな」と思った時の体の反応(心臓がバクバクする、胃が重いなど)を無視しない。
✅ 2. 小さなNOを練習する
• 断るのが怖ければ、「今日は難しい」「考えてみるね」などワンクッション置く言葉から。
✅ 3. 距離を物理的に取る
• LINEの返事を遅らせる
• 会う回数を減らす
• 安全のために共通の知人と一緒に会う
✅ 4. 助ける基準を持つ
• 「その人が自分でも解決できることは手を出さない」
• 「自分の生活や夢を犠牲にしない」
✅ 5. 優しさの定義を変える
• 「相手の自立を応援することこそ優しさ」と思えるようになる。
🟦 まとめ:優しさはあなたを守ることから始まる
「助けすぎ」「優しすぎ」のループは、あなたが弱いからではなく、教育やトラウマが作った自動反応です。
その自動反応に気づき、CBTのワークで整理し、境界線を引く練習をすることで、少しずつ優しさの形を変えていけます。
本当の優しさは「自分を犠牲にすること」ではなく、
「自分も相手も守れるバランスを見つけること」なのです。
次回は
🌀第6回🌀危うい相手と自分を科学する:距離感を守るための具体的なステップ[機能不全家族シリーズ2]
です
👩いかがでしたか?
今回も最後までお読みくださりありがとうございました。
ご意見ご感想など、どんなコメントでもいただけると嬉しいです。
次回もまたお会いしましょう!
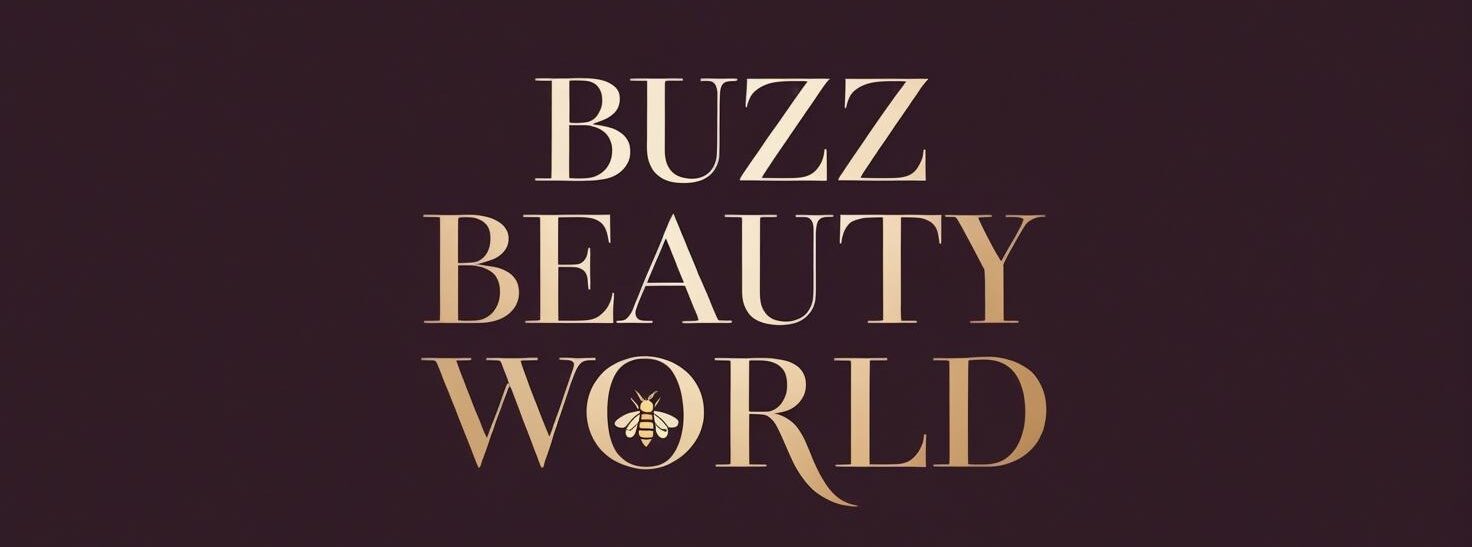


コメント