🟦【はじめに】
「腸活のために発酵食品や食物繊維をとっているのに、あまり効果が感じられない…」
そんな方にこそ注目してほしいのが、**“噛むこと”=咀嚼(そしゃく)**です。
実は、よく噛むことが腸内環境を整える鍵になるのをご存じでしょうか?
この記事では、
• 噛むことが腸に与える3つの効果
• 噛まないことがもたらすリスク
• 早食いを治すための習慣術
をわかりやすくまとめました。
🟦【1】なぜ“噛む”ことが腸活に効果的なのか?
✅📌① 唾液が消化のスタートラインを整える
噛むことで分泌される唾液には、消化酵素(アミラーゼ)が含まれており、
胃や腸の負担を軽減してくれます。
→結果:腸が疲れにくくなり、栄養吸収率もアップ!
✅📌② 食べ物が細かくなり、腸での分解がスムーズに
よく噛むことで、食べ物が細かく砕かれ、胃から腸へとスムーズに送られます。
これにより、ガスや便秘、腸内発酵のトラブルが起きにくくなります。
✅📌③ 脳が「満腹」を感じやすくなり、腸への負担も減る
しっかり噛むことで、満腹中枢が適切に働くため、
食べ過ぎによる腸内の過剰発酵や未消化物の滞留も防げます。
🟦【2】噛まない生活で腸が乱れ肌まで荒れる?見落とされがちなリスク
✅📌・唾液が少ない=消化酵素不足
→ 唾液が少ないと口の中が乾燥しやすく、口臭・虫歯・歯周病になるリスクが高くなります。
また、消化酵素が少ないことにより、胃もたれ(腸が疲れる)の原因になります。
✅📌・大きなまま飲み込む
→ 腸が未消化物を処理しきれず、胃や腸の負担になり消化不良を引き起こします。
未消化のままの食べ物が多いと悪玉菌が増えやすくなり腸が乱れてしまいます
✅📌・早食いで食べ過ぎる
→ 早食いをすると空気を一緒に多く飲み込んでしまいます。(呑気症)
飲み込んだ空気が口から出ればゲップ、足裏から出ればオナラです。
腸内ガスが増えると腸内環境のバランスを崩し、便秘や下痢の原因となります。
また胃や腸の膨満感によるストレスは自律神経も乱しやすく、腸のぜん動運動を低下させる原因に。
早食いは、唾液に含まれる美肌成分の恩恵を減少させるだけでなく、腸内環境の悪化に伴い肌荒れなどの原因に。
特に現代人は「スマホを見ながら」「仕事の合間に急いで」など、無意識の早食いが日常化しがちです。
🟦【3】早食いを治すためのアイデア5選|今日からできる!
✅📌① 一口ごとに箸を置く
→強制的にリズムがゆっくりになり、「噛む時間」が生まれます。
✅📌② 咀嚼回数を「目安20〜30回」にしてカウントしてみる
→意識づけだけで、胃腸の疲れが減ると感じる方も多いです。
✅📌③ 固めの食材や食感のある食材を増やす
→よく噛まないと食べられない食品を意図的に選ぶ。
- ごぼう
- 蓮根
- 海藻類
- 切り干し大根
- きのこ類
✅📌④ 音楽や照明で「食事を楽しむ空間」を作る
→心のゆとりがあると、自然と噛む時間も増えます。
✅📌⑤ スマホやテレビを見ながらの「ながら食べ」をやめる
→集中力を食事に向けるだけで、噛む意識が上がります。
🟦【4】噛むこと×腸活|おすすめの食材
✅📌・玄米ごはん(白米より噛む回数が増える)
✅📌・りんごや干し芋、ナッツ(食感がしっかり)
✅📌・雑穀入りおにぎり、切り干し大根のサラダなど
食材の選び方ひとつで「噛む習慣」が自然に育ちます。
🟦【まとめ】「よく噛む」は最高の腸活
忙しい現代こそ、「ゆっくり噛む」という習慣は、心と体の健康を取り戻す鍵。
しっかり噛むことで、
✔消化の助けになる
✔腸の負担を減らす
✔腸内細菌バランスが整う
✔便通が良くなる
✔肌・メンタルも安定しやすい
というように、“腸をいたわる最初の一歩”は、口からはじまります。
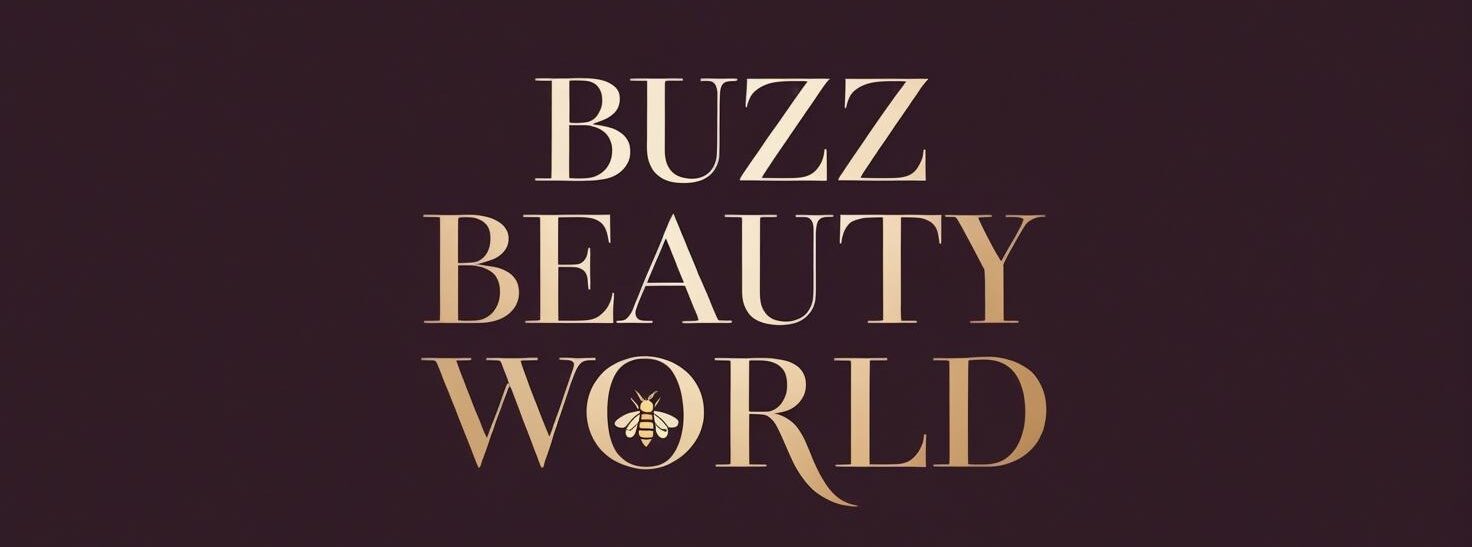



コメント