🟦【はじめに:食欲は“脳”ではなく“腸”が決めている?】
「無性にチョコレートが食べたくなる」
「食べたい気持ちが抑えられない」
こうした衝動の背後には、“腸と脳を結ぶ科学的な回路”が存在しています。近年の研究で、腸内細菌が脳に指令を送り、食の選択を左右しているという事実が解明されつつあります。
本記事では、その根拠を最新の研究論文とデータに基づいて深掘りしていきます。
食後の血糖値の上昇を抑える!飲むグアーガム リフリーラ🟦【1】腸内細菌は神経伝達物質を作っている
✅📌腸はセロトニンの製造工場
• 幸せホルモン「セロトニン」の約90%以上が腸で作られている(Gershon MD, 1998)
• セロトニンは食欲、気分、睡眠などに関与
✅📌腸内細菌が神経伝達物質を生産
• 乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌は、セロトニンやドーパミン、GABA(抗不安作用がある神経物質)などを産生
• これらの物質は迷走神経や血液脳関門を通じて脳に届く
📘参考文献:Cryan JF et al. (2012). Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. Nat Rev Neurosci.
🟦【2】腸内細菌は「迷走神経」を通じて脳に影響を与える
✅📌迷走神経とは
• 腸と脳を結ぶ双方向通信回路
• 腸から送られた信号が脳に届き、行動や情動に影響
🧠例:
• マウスの実験で、腸内細菌のない無菌マウスは行動が異常になることが判明
(Sudo et al., 2004)
• 腸内に特定の菌を移植すると、食行動やストレス反応が変わる
🟦【3】腸内細菌は「自分のエサ」を得るために行動を操作する?
✅📌細菌も“生き延びたい”
→ 糖を好む菌(例:カンジダ属)は、宿主に甘い物を欲しがらせる
→ 繊維をエサとする菌(例:バクテロイデス)は、野菜を食べたくさせる
📌根拠:
• **Alcock et al. (2014)**の論文では、腸内細菌が宿主の食欲・情動・味覚を操作し得るとされている
“Microbes may manipulate host behavior to increase their own fitness.”
(訳:微生物は自らの生存のために、宿主の行動を操作することがある)
🟦【4】「腸内環境の悪化」が欲求を乱すメカニズム
✅📌悪玉菌優位になると:
• 炎症性サイトカインが増え、脳の報酬系が過敏になる
• 結果として、中毒的に甘い・脂っこい物を欲する
✅📌腸内フローラの乱れは「過食・不安・うつ」の温床に
• 腸内細菌の多様性が低いと、メンタル不調や衝動的な食欲に繋がりやすい
• 腸内の炎症は、脳にも炎症反応を波及させる(“leaky gut → leaky brain”理論)
📘参考:Kelly et al., 2015. Transferring the blues: Depression-associated gut microbiota induces neurobehavioral changes in the rat.
🟦【5】逆に「腸を整える」と欲求が変わる理由
✅📌プレバイオティクス(食物繊維やオリゴ糖)を摂取すると:
• 善玉菌が増殖
• 短鎖脂肪酸(酢酸・プロピオン酸・酪酸)が産生され、脳に届き「満腹・安心」を促す
✅📌プロバイオティクス(菌そのもの)摂取による行動変化
• ある研究では、乳酸菌を含むヨーグルト摂取で情緒安定&意思決定が改善したという報告も(Tillisch K. et al., 2013)
🟦【6】まとめ|腸と脳は「共犯関係」にある
📌 食欲は、脳のみによって決まっているわけではなく、腸内細菌の影響を大きく受けている
📌 私たちは、“腸に操られている”というよりも、腸との共生関係の中で選択している
🧠つまり:「脳と腸はチーム」であり、「食の選択はチームワークの結果」なのです。
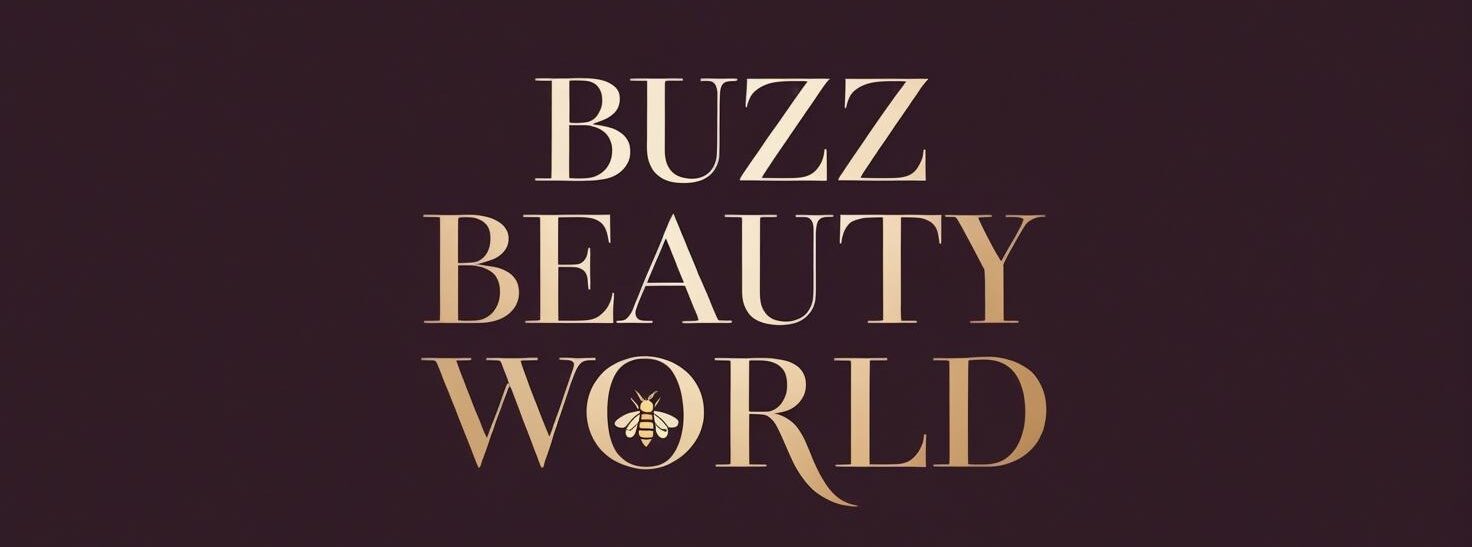



コメント