この記事の結論ポイントを先に
MCTオイルは…
🧬 ケトン体による抗炎症作用が脂肪肝の進行を抑える可能性
🧠 糖質制限中の脳エネルギー補給にも有効
⚠️ 既に肝臓が弱っている人や脂肪肝に罹っている方には悪化の可能性あり。医師の指示のもと慎重な判断が必要。
詳細は、本文をご覧ください。
🟦 糖質制限で起こる“耐糖能低下”と脂肪肝のリスク
✅ 糖質制限がもたらす代謝の変化
- 長期の糖質制限により、インスリン感受性が低下し「耐糖能」が落ちることがある A
- 少量の糖質でも過剰なインスリン分泌が起こり、反応性低血糖や過食欲求につながる
- 糖代謝がうまく働かないことで、脂肪が肝臓に蓄積し「脂肪肝」になるリスクが上昇
🟦肝炎・脂肪肝を放置すると肝硬変、肝臓がんへ進行する
✅肝炎や脂肪肝が進行して肝硬変や肝がんになるメカニズム
🧬 肝疾患の進行メカニズム
| 段階 | 内容 |
| 脂肪肝 | 肝細胞に脂肪が蓄積。初期は無症状だが、放置すると炎症を引き起こすことがある |
| 脂肪性肝炎(NASH) | 肝細胞が炎症を起こし、損傷が進行。非アルコール性脂肪性肝疾患の一部。 |
| 肝線維化 | 炎症が続くことで、肝細胞が破壊され、修復の過程で線維(硬い組織)が蓄積。 |
| 肝硬変 | 線維化が進行し、肝臓の構造が変化。血流障害や機能低下が起こり、回復が困難になる。 |
| 肝がん(肝細胞がん) | 長期の炎症と細胞損傷により、遺伝子異常が蓄積し、がん化するリスクが高まる。 |
🔍 なぜ進行するのか?
- 慢性的な炎症:肝炎ウイルス(B型・C型)や脂肪肝による炎症が長期化すると、肝細胞が繰り返し破壊・再生されます。
- 線維化の蓄積:再生の過程で線維が蓄積し、肝臓が硬くなっていきます。
- 遺伝子の損傷:炎症による酸化ストレスや免疫反応が、肝細胞のDNAにダメージを与え、がん化の引き金になります。
⚠️ 注意すべきポイント
- 肝臓は「沈黙の臓器」「サイレント・キラー」と呼ばれ、症状が出にくいため、気づいたときには進行していることが多いです。
- 脂肪肝でも油断は禁物。NASHに進行すると、肝硬変や肝がんのリスクが高まります A。
- ウイルス性肝炎は、抗ウイルス治療で進行を抑えられる可能性があります。
💡予防のカギは
生活習慣の改善(食事・運動)と定期的な検査(健康診断など)です。気になる症状やリスクがある場合は、早めに医師に相談するのが安心です。
🟦 MCTオイルの作用と肝炎・脂肪肝への影響
✅ MCTオイルの代謝経路
- 中鎖脂肪酸は小腸から門脈を通じて直接肝臓へ運ばれ、すぐにエネルギーとして使われる C
- 脂肪として蓄積されにくく、ケトン体生成を促進する
✅ 脂肪肝に対するポジティブな研究結果
- 京都大学の研究では、MCTが肝臓の炎症や線維化を抑制する可能性が示唆されている B
- GPR84という受容体を介してマクロファージの過剰活性化を防ぎ、脂肪肝の進行を抑える
✅ 注意すべき点:肝臓への負担
- MCTは肝臓に直接届くため、肝機能が低下している人には負担になる可能性も D
- 摂取量が多すぎると、肝臓に過剰なエネルギー負荷がかかることがある
⚠️つまり⚠️ 体質によっては逆効果になることも
- MCTオイルの摂取で脂肪肝が悪化したという報告も一部存在 D
- 特に糖質制限で代謝が乱れている人は、慎重な導入が必要
🟦 おすすめできるか?体質別に判断しよう
✅ おすすめできるケース
- 肝機能が正常で、糖質制限を継続している人
- ケトジェニックダイエット中で、エネルギー補給が必要な人
- 医師の指導のもと、脂肪肝予防として少量から導入する場合
✅ おすすめできないケース
- 肝機能が低下している人(肝炎・脂肪肝が進行しているなど)
- 耐糖能が著しく低下している人(反応性低血糖の症状がある)
- 糖質制限を解除したばかりで代謝が不安定な人
✅摂取のポイント
- 初めは1日2g程度からスタートし、様子を見ながら増量 B
- 通常の油と置き換える形で使う(カロリー過多を防ぐ)
- 朝食に取り入れると代謝が安定しやすい
🟦 まとめ:MCTオイルは“万能”ではないが、使い方次第で味方になる
📌 賢く使うための3ステップ
- 自分の肝機能と糖代謝状態を把握する
- 少量から始めて体調を観察する
- 医師や栄養士と相談しながら使用する
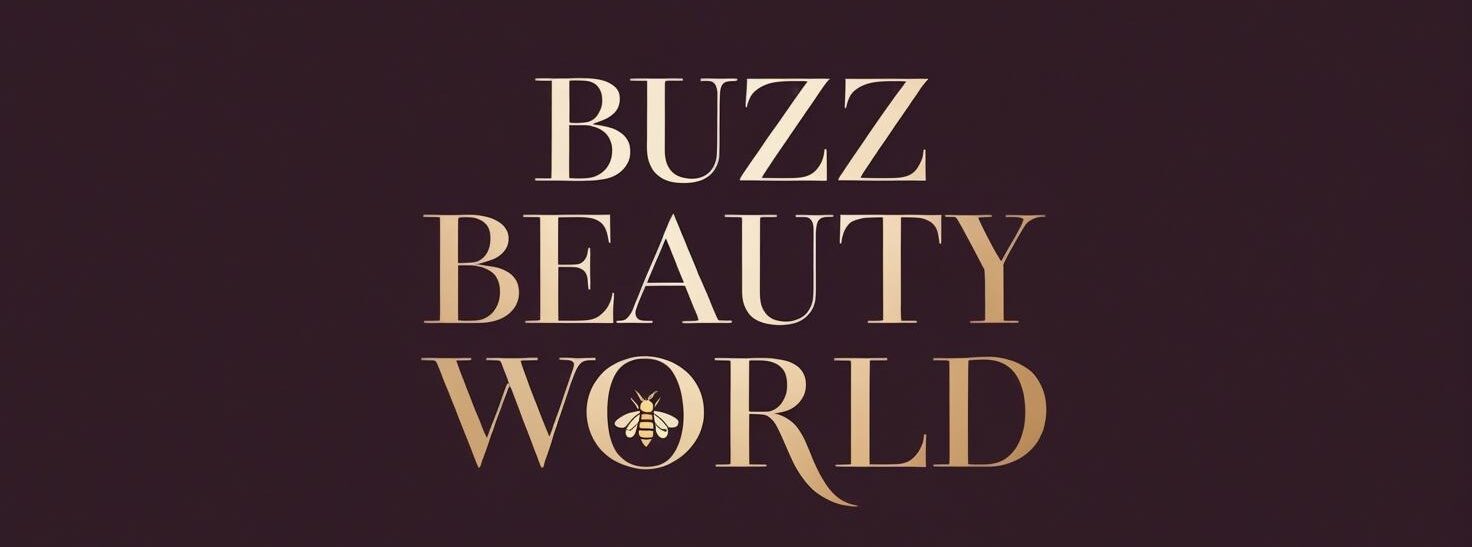



コメント