🟦「体が硬い」と感じるのは、筋肉だけの問題じゃない
「前屈で手が床につかない」「しゃがむと膝が突っ張る」
そんな“硬さ”の正体は、筋肉だけでなく関節や神経、靭帯など複数の要素が関係しています。
柔軟性と関節可動域は似ているようで違うもの。
この回では、柔軟性と可動域の違いを整理しながら、安全に動ける身体づくりのための実践法を紹介します。
🟦柔軟性と関節可動域の違いとは?
| 用語 | 定義 | 例 | 出典 |
| 🟩柔軟性(Flexibility) | 他動的に関節が動く範囲 | 他人に押してもらって前屈する | https://yuji163.com/flexibility-and-mobility/ |
| 🍀可動性(Mobility) | 自分の力で関節を動かせる範囲 | 自力で前屈して足裏を掴む | https://aoki-training.com/2019/01/18/柔軟性が高いからといって関節の可動性が高/ |
✅柔軟性が高くても
自力で動かせないと怪我のリスクが高まることもあります
✅理学療法士やトレーナーは
理学療法士やトレーナーは可動性の向上こそが安全な動作の鍵と考えています
🟦関節可動域を制限する3つの要因(Joint by Joint Theory)
| 制限因子 | 内容 | 例 | 出典 |
| 🟩主導筋の弱さ・拘縮 | 動かす筋肉が弱い・固まっている | 腸腰筋が弱くて股関節が曲がらない | https://aoki-training.com/2019/01/18/柔軟性が高いからといって関節の可動性が高/ |
| 🍀拮抗筋の硬さ | 反対側の筋肉が伸びない | ハムストリングが硬くて前屈できない | 同上 |
| 🌍安定関節の機能不全 | 隣接する関節が不安定で動きが制限される | 骨盤が不安定で股関節が動かない | 同上 |
🟦柔軟性と可動域を高めるための実践法
| 方法 | 目的 | 実践例 |
| 🟩ダイナミックストレッチ | 可動性向上・筋温アップ | 股関節回旋・肩回し |
| 🍀スタティックストレッチ | 柔軟性向上・筋緊張緩和 | 太もも裏・ふくらはぎの静的伸張 |
| 🌍筋膜リリース | 滑走性改善・癒着予防 | フォームローラーで背中・太ももをほぐす |
| 🟩モビリティドリル | 関節の自動可動域拡大 | 四つ這いでの肩・股関節の動作練習 |
🔗参考:https://www.sakuma-ebisu.jp/2527/
🔗参考:https://e-trend123.com/archives/2674
🟦柔軟性を高めるだけでは不十分?注意点と落とし穴
✅柔軟性だけが高いと
柔軟性だけが高いと、関節が不安定になり怪我のリスクが増す
✅特に女性や若年層は
特に女性や若年層は、弛緩性(関節の緩さ)が高い傾向があり、可動性とのバランスが重要
✅「柔らかい=安全」ではない?
「柔らかい=安全」ではなく、動きをコントロールできる範囲を広げることが安全につながる上で大切
🔗参考:https://yuji163.com/flexibility-and-mobility/
🟦日常でできる柔軟性&可動域アップ習慣
| シーン | 工夫 | 効果 |
| 🍀朝のルーティン | ダイナミックストレッチ | 1日の動作がスムーズに |
| 🌍仕事の合間 | 30分ごとに姿勢を変える | 関節の硬化予防 |
| 🟩入浴後 | スタティックストレッチ | 筋緊張の緩和と柔軟性向上 |
| 🍀週末 | モビリティドリル+筋膜リリース | 関節の滑走性と可動性を改善 |
🟦まとめ:柔軟性と可動域は“動ける身体”の両輪
柔軟性は「伸びる力」、可動域は「動かす力」。
どちらかだけでは不十分で、両方をバランスよく高めることが、安全で快適な身体づくりの鍵です。
次回は【連載・第7回】として、加齢と骨筋機能の変化について掘り下げます。
👩完璧を目指すのではなく、できることからコツコツとやっていきましょうね。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
ご意見ご感想をいただけると嬉しいです。記事のリクエストもお待ちしています!
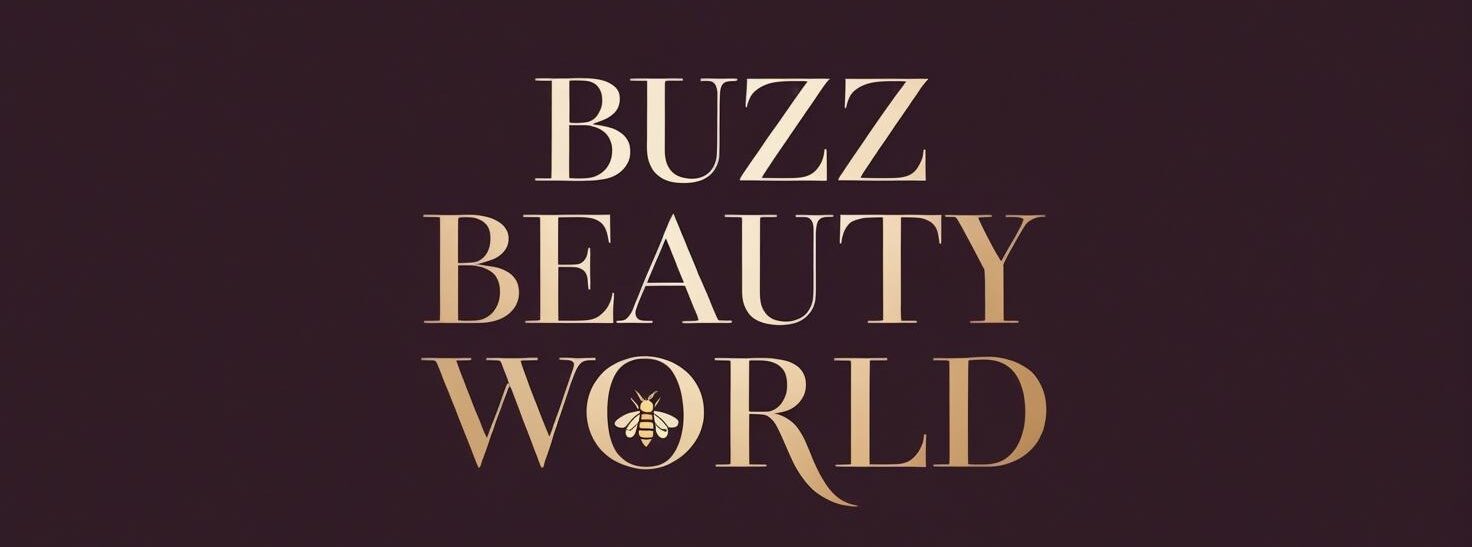
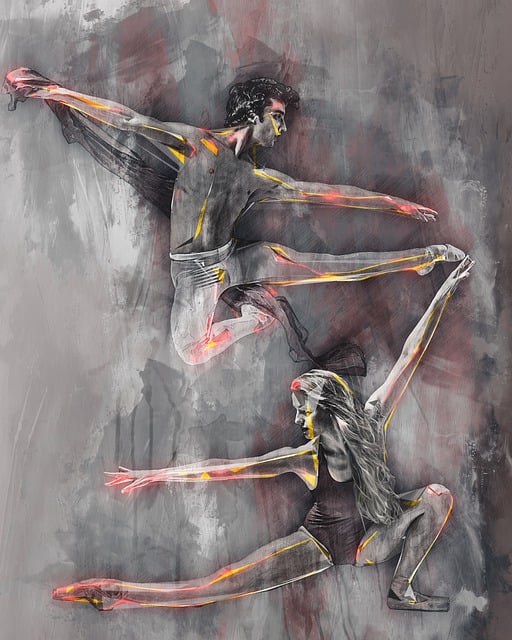


コメント